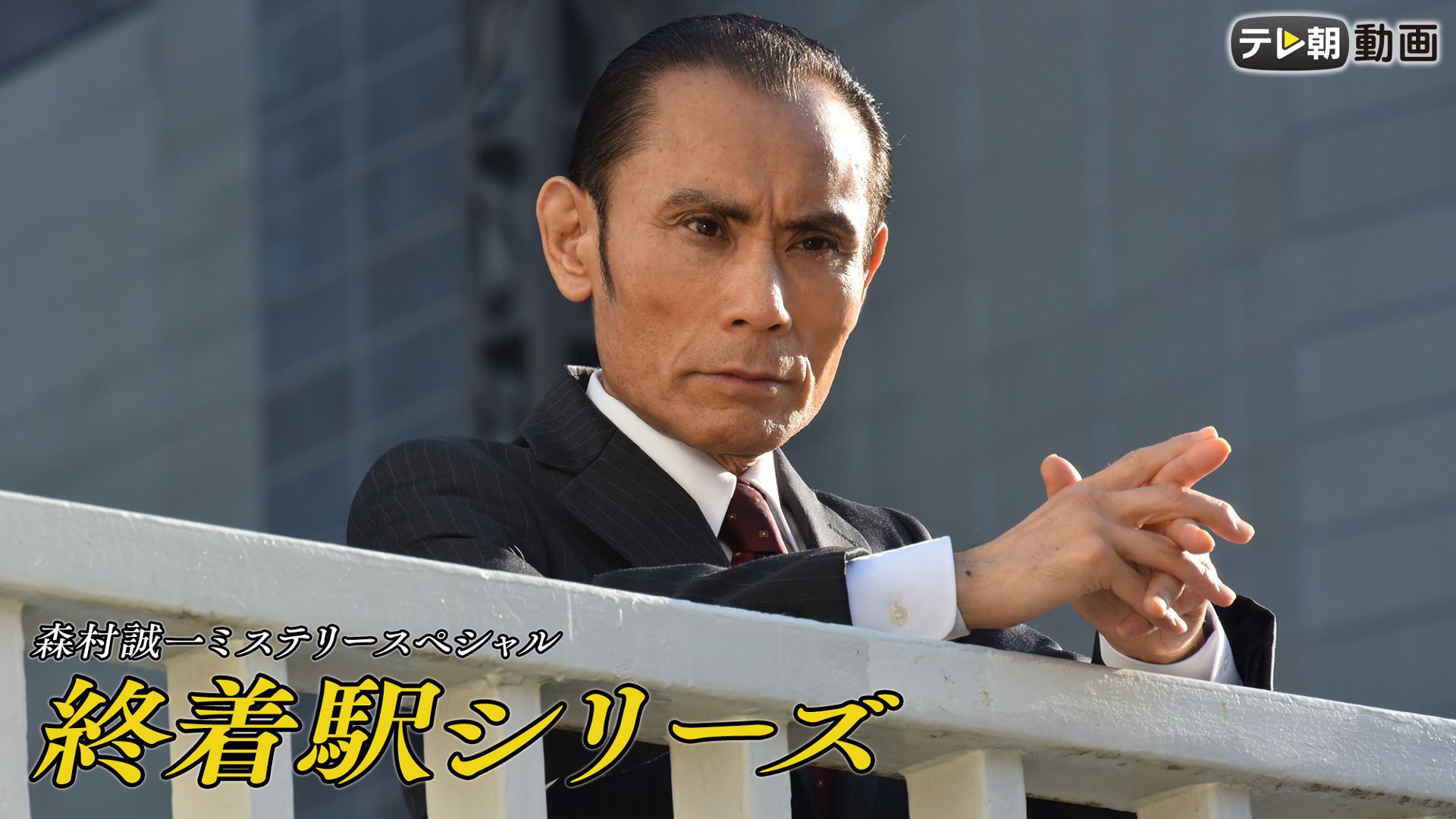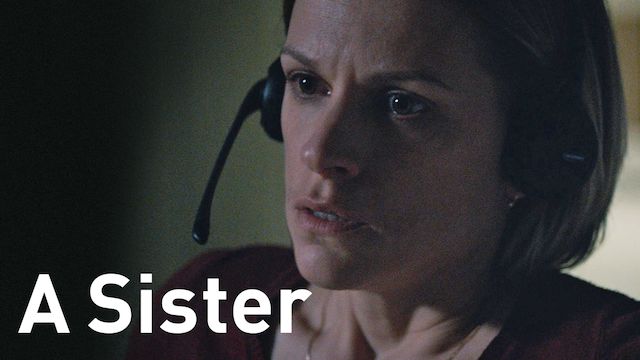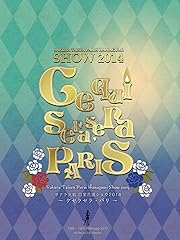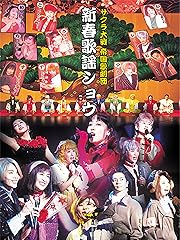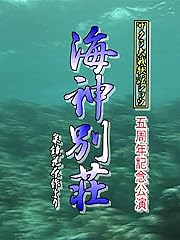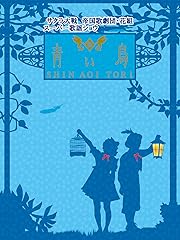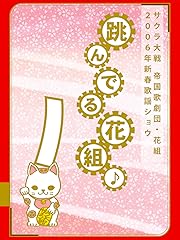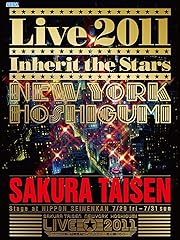まだ閲覧した作品がありません

作品詳細ページを閲覧すると「閲覧履歴」として残ります。
最近の見た作品が新しい順に最大20作品まで表示されます。
-
追加日:2020.2.7
いまだグラビア界の第一線を走る西田麻衣ちゃんのIカップが弾ける! アラサーになり、豊満ボディからますますフェロモンを放つ西田麻衣。撮影時は天候に恵まれず、ビーチロケはなくなったが、それを補って余りあるセクシーショットを連発。 部長であるあなたと沖縄に出張でやってきた西田麻衣。部長を部屋に招き入れ、何やら誘惑目線で衣装を脱ぎだす。黄色のワンピース水着、紫の小さめビキニなどをまとい、セクシーな表情を浮かべる。浴室では、やはりビキニ姿であなたを洗い始め…。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.2.10
少女から妖艶な女へ…。アイドリング!!!の元メンバー・高橋胡桃のイメージ 谷崎潤一郎の不朽の名作に、高橋胡桃が挑戦。『痴人の愛』の物語をなぞり、高橋胡桃が無垢な少女から男を翻弄する悪女への変貌を表現し、その蠱惑的な肢体のとりこになる。 男のもとに訪れた無垢な少女・ナオミ。西洋人形のような容姿、純真な笑顔を浮かべる少女は、男と寝食を共にするうちに、次第に妖艶な女へと成熟する。美貌を際立たせるメイク、はだけた着物からのぞく胸の谷間、あふれ出る色香で観る者の理性を狂わせる。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.2.10
第二次世界大戦の軍事作戦を科学的に取り上げ、隠された真実に迫るドキュメンタリー 光センサー技術、写真測量、遠隔操作による探知技術などの最新テクノロジーを駆使し、科学的に戦争を見つめることで、戦争という悲劇を改めて考えることができる。 人類史上、最も大規模で破滅的な戦争である第二次世界大戦。軍事作戦の多くは、戦争の不透明さや政治情勢によって誤って伝えられてきた。そうした戦争の実態を最新科学を用いて解説し、軍の記録や証言により周知されている事実とは違う側面を明らかにする。
-
追加日:2020.2.10
写真家、ビデオディレクター、コントリビューター、フォトエディターなど、様々な顔を持つパトリック・オーデル (Patrick O’Dell) がつづるスケートボーダーのドキュメントシリーズ『Epicly Later’d』。今も昔も、スケーターはただのバカだってことは変わらないが、本物のスケーターは他では替えがきかない。このスケーターであるべきで、なぜ他のスケーターじゃダメなのか。VICEのWEBシリーズとして長らくスケートファンに親しまれてきた同作が、新たなエピソードを携え米国テレビ放送向けに復活。
-
追加日:2020.1.30
第一次大戦に出征した若者たちを通して戦争の矛盾や葛藤を映し出した戦争ドラマ ルイス・マイルストン監督による同名作品を、『マーティ』のデルバート・マン監督がリメーク。若い兵士たちが夢見ていた“英雄”のいないリアルな戦争の悲惨さが胸を打つ。 第一次世界大戦が始まって間もない頃。ドイツの学校で教師は生徒たちに愛国主義を説き、情熱に駆り立てられた若者たちは、出征を志願する。入隊後、彼らは過酷な訓練を受け、戦場へと送り出されるが、前線で待っていたのは飢えと恐怖に脅かされる日々だった。
 Amazonプライムビデオで今すぐ観る
Amazonプライムビデオで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.17
美少女系グラビアアイドル・森野朝美ちゃんがキュートな笑顔を魅せる! 畳の部屋で寝そべる朝美ちゃん。きれいな足、ボリュームのある胸元をカメラがキャッチ。セクシーな下着姿で体をくねらせ、ドキドキしちゃうようなささやきも発する。 1995年生まれで身長は160cm、スリーサイズは上から82、60、87cmという森野朝美ちゃん。正統派のアイドルフェイスと均整の取れたボディが売りだ。本作は10代からグラビア活動をしている彼女が確実に成長している証となっている。艶やかな表情は見逃せない。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.17
死んだはずのジヴァがカムバック!物語はさらなる展開を見せる第17シーズン 第1話と第2話はジヴァが主演のエピソードで、死んだと思われた彼女が本当に生きていることが明らかに。ジヴァとの再会をきっかけに変化していくメンバーたちの姿にも注目。 精神的に追い詰められ、自首を決意したギブスの前に死んだはずのジヴァが現れ、ギブスの命が危ないと警告する。一方、マクギーたちもジヴァが生きていることを知り、再会を果たす。だが、それをきっかけに、それぞれが複雑な想いを抱えるようになり…。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.17
フランス南部。城壁に囲まれた美しい村で暮らす、野生動物の1年を絵本のような幻想的な映像でつづる。春にかけて冬眠していた動物が目覚める中、屋根裏部屋に棲みついたオオヤマネは、約8ヶ月も冬眠をするためまだ眠っていた。初夏から真夏にかけて、アオガラはひなへの給餌で大忙し、渡り鳥のチゴハヤブサはトンボを捕食していた。秋が訪れると、動物は冬支度を始める。人間の世界と野生動物の暮らしが絶妙に共存する姿をお届け。
 Huluで今すぐ観る
Huluで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.17
フランスの田舎を舞台に、養豚家の青年の日常をセンチメンタルに描いた短編コメディ 世界中で展開されるフランス映画のオンライン映画祭「第10回マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバル」出品作品。菜の花畑が広がるフランスの田園風景が美しい。 フランスの菜の花畑が広がる田舎で暮らすミカエルは、行方不明のブタを見つけること、オーガニック認証を受けること、そしてアブラナに囲まれた孤独な人生から抜け出したいと思っていた。そんなある日、魅力的なポールが田舎に帰ってきて…。
-
追加日:2020.1.17
映画好きの若者が、幼馴染みと時に衝突しながら映画を作る様子を描いた短編映画 世界各国で展開されるフランス映画のオンライン映画祭「第10回マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバル」招待作品。新鋭、ヤシン・クニアが監督と脚本を担当した。 熱心な映画ファンである若者のヤシンは、生まれ育った地元で映画を撮りたいと思っている。そして、自分の幼馴染みたちを映画プロジェクトに参加させようとするのだが、時に友情には欠点がついてくる。それぞれの思惑がぶつかるなか、映画の行く末は…。
-
追加日:2020.1.17
大自然の中で生き、その土地で自給自足を続ける人々のサバイバルを映すシリーズ第3弾 ワイルドな山男たちの生き方は相変わらず衝撃的。また家族のことを思って進退を考えたり、狩猟技術を息子に伝えたりと、将来を見据えた行動に胸を打たれる。 広大なアメリカの大地。そのなかには、わなを仕掛けて狩猟し、家族のためにその土地で自給自足を続けている人々がまだ存在する。アパラチアやロッキー山脈、アラスカなどに生きる男たちが、必要な食物や資金を確保し、厳しい冬に備えていくさまを映していく。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.17
帝國歌劇団・奏組を、歪で哀しい旋律が襲う。舞台『サクラ大戦奏組』第2弾 チームワークが大幅にアップした奏組のパフォーマンスは必見。第1弾にはなかった主人公・音子のソロ歌唱パートがあったり、さまざまな衣装にチェンジするのも見どころ! 大帝國劇場の帝國歌劇団・奏組に指揮者として配属されてしまい、同時に魔障陰滅部隊・奏組の隊長にも任命されてしまった雅音子。その生活にもようやく慣れて来たある日、帝都を脅かす新たな敵・デノンマンサーが音子、そして奏組の前に立ちはだかる。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.17
『サクラ大戦』初の舞台化作品は、「奏組」の活躍を描く新たな大正浪漫活劇! 原作は島田ちえの漫画『サクラ大戦奏組』。シリーズ初の少女漫画・女性向け作品となり、キャストもイケメンが勢ぞろい。奏組でしか成しえない楽曲の数々に要注目! 憧れの帝國歌劇団・花組に入ることを夢見て帝都へ上京した雅音子。しかし荷物を盗まれ、荷物を探しさまようことに。一方、大帝國劇場では、男性のみのオーケストラ「奏組」に雅音子が加入し、指揮者を務めることを知らされる。音子と奏組を待つ運命とは?
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
ジロウ、くり、松本バッチによる世界で最もピュアな実戦番組! パチスロの腕前はもちろん、トーク力もあるジロウ、くり、そして松本バッチ。仲が良いのか悪いのかはよくわからないが、掛けあいの面白さは実戦番組の中でも随一だ。 出演するのはジロウ、くり、そして松本バッチ。個性的な面々がパチスロを通じて仲良くなろうという企画。もちろん狙うのはビッグな出玉だ。ところが、ノリ打ちにするのかしないのか、などがオープニングの段階でも決まっていなかったり、波乱含みだ。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
BS笑点ドラマスペシャル第3弾は、いよいよ初代林家木久蔵の登場! 笑点・大喜利レギュラーメンバーは、魅力的なキャラクターの宝庫ですが、中でも「この人なくして笑点・大喜利なし」とまで言わしめたのが林家木久蔵 (現・木久扇) です。回答者としての出演期間は、今年でなんと50年目に突入、最古参の大喜利メンバーになりました。不動の“おバカキャラ”を貫き、異彩を放ち続ける林家木久扇。しかし当初は無個性で特徴がなく、レギュラー回答者から降ろされる寸前までいったことがあるのです。“おバカのスーパースター”林家木久扇の知られざる、原点を描きます!
 Huluで今すぐ観る
Huluで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
死刑囚となった女性の無実を信じる幼馴染みの目線から描いたヒューマンサスペンス 早見和真の同名ベストセラー小説を、妻夫木聡主演で映像化。人々の悪意にさらされ続けた女性死刑囚を竹内結子が好演。監督は『愚行録』で妻夫木とタッグを組んだ石川慶。 佐々木慎一は、幼馴染みの田中幸乃が元交際相手の住むアパートに火を放ち彼の妻子を焼死させたとして、死刑判決を受ける姿を法廷で見つめていた。幼少期の幸乃を知り、そしてある負い目を持つ慎一は、彼女の無実を信じ、幸乃の人生を知る人々に会いに行く。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
3人の絆は、本物?メジャーデビューを目指す少女たちの奮闘を描くドラマ第3シーズン 今シーズンで最終章を迎える本作。逆境や困難にぶつかりながら夢を追う3人の姿に最後まで目が離せない。レニー・クラヴィッツとナオミ・キャンベルがセレブ夫婦役で登場。 ひとりきりのステージを経験し、仲間の大切さを痛感したスター。あれから3カ月、ツアーを終えてアトランタに戻ったスターは、ある重大な秘密を抱えていた。一方、カルロッタとキャシーの溝は埋まらないまま、母親のクリスティーンが板挟みになってしまう。
-
追加日:2020.1.20
大野さえこの色白むっちりマシュマロボディがバリでさく裂! 群馬クレイサンダーズ公式応援ユニットLTCメンバー・大野さえこが、開放的なバリの空と海を背景に弾ける。むっちりとした肉感とセクシーポーズで迫る姿に誰もがメロメロ。 抜群のプロポーションはもちろん、競泳水着やキュートな水着、メイド風コスチュームや小さめビキニまで、さまざまなコスチュームで見せるちょっぴりセクシーなポージングにくぎづけ。南国の開放感からどんどん大胆になっていく姿を見逃すな。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
超美形フェイスにGカップバストがまぶしいグラビアアイドル・海里のデビュー作 初イメージ作品にして、清楚なお姉さんの印象を裏切るような大胆な姿をたっぷり披露する。過激な衣装で開脚、際どいアングルからの撮影など、攻めた構成に目を見張る。 デビューすると同時に2019年のグラビア界を席巻したグラビアアイドル・海里。元企業の受付嬢という彼女の整った顔立ち、まぶしい笑顔、そして大胆過激な衣装とポージングの数々に魅了される。水着からこぼれ落ちそうなGカップの胸から目が離せない。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
エロかわいい現役エステティシャン・加藤圭が自慢のテクニックであなたを落とす!? 甘い声でささやきながら、いかにもな手つきでシャワーヘッドをなで回す加藤圭。童顔の彼女が時折挑発的な視線を投げかけながら、美ボディを見せ付ける仕草にノックアウト。 競泳水着姿の加藤圭が棒アイスを舐めながら、股間に手を伸ばし、悩ましい表情を見せる。今度は網タイツに手を入れモソモソ。さらに衣服を脱いでいき、パンティをゆっくりずらしていく。制服姿では、先輩に告白し、下着姿でお尻を見せ付けてしまう。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
1937年に突如消息を絶った女性飛行士の失踪の謎に迫るドキュメンタリー 人気の高さゆえに失踪について都市伝説までささやかれるアメリアの行方を、確かな実績を持つ冒険家が探る。1937年から語られるミステリーの答えを導けるのか注目だ。 女性初の大西洋単独横断飛行など、伝説を打ち立てたアメリア・イアハート。赤道上の世界一周飛行に挑戦中に消息を絶った彼女の飛行機を見つけ出すため、海洋冒険家、ロバート・バラードが太平洋に浮かぶとある島を訪れ、あらゆる方法で探索していく。
-
追加日:2020.1.20
好奇心旺盛なお嬢さま・白宮奈々ちゃんは、小柄ながら豊満なボディの美少女! 上品な雰囲気の奈々ちゃんが、麗しい肉体を大胆披露。身長151cmのミニマムボディながら、しっかり育った丁度良いサイズのバスト、明るく元気な笑顔が男心を刺激する。 白宮奈々ちゃんが高級そうなワンピースの下に隠された、VIPな秘密の花園を開放。弾ける笑顔からじっくりと素肌を露わにする悩ましげな表情にくぎづけ。ブラスバンド部に所属していた奈々ちゃんが、学生時代を思わせる制服姿であなたを誘惑する。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
現役歯科衛生士グラドル・西原愛夏ちゃんがFカップバストで悩殺! 歯科衛生士とタレントの二足のわらじ生活を続けている才女・西原愛夏ちゃん。白衣の下に隠していた、B90cm・W58cm・H86cmのグラマラスボディは見逃せない。 美人度が際立つスポーティーなブラと短パン姿で登場の愛夏ちゃん。バスルームでは三角ビキニでまったり。女性的な体のラインが強調されるレオタード姿は、まさに目の保養。ベッドによこたわり、妖艶な眼差しを向ける愛夏ちゃんから目が離せない。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
明るく元気なお嬢さま・白宮奈々ちゃんのミニマム美ボディを大公開! ミスFLASH2020グランプリに輝いた人気グラドル・白宮奈々ちゃん。身長151cmと小柄ながら、たわわに実ったFカップバストを大胆なポージングで見せつける。 お上品でかわいらしい容姿でも体は大人な奈々ちゃん。スパッツを穿いてもらったところ、お嬢さまの柔らかそうな太腿とお尻のラインがくっきり浮きでてしまう問題が発生。慌てて薄々のチューブトップビキニに着替えてもらうと、もっと大変なことに!?
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
スレンダーなのにマシュマロHカップの麻亜子がお風呂でゆったり! ミスFLASH史上初めて一般応募から2018のグランプリに輝いた麻亜子。前職はウェブデザイナーで、自らのサイトを立ち上げた彼女が、才女の片りんを垣間見せる。 競泳水着で登場した麻亜子は、Hカップの横乳を見せながらにっこり。ベッドでごろごろしたり、お尻を突き出して挑発的なポーズを繰り出す。今度はTバックのセクシー下着姿で風船遊び。さらにけん玉やフラフープを披露し、ベッドで悩ましい視線を投げかける。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
人懐っこい現役歯科衛生士グラビアアイドル・西原愛夏ちゃんのイメージ 歯科衛生士として働き、キリッとシャープな印象の愛夏ちゃんが服を脱ぎ、露わになった柔らかそうな胸とお尻にドキドキ。クールさとキュートさのギャップにとりこになる。 一見クールそうだが、ゆるかわいい西原愛夏ちゃんがバスト90cm、ウエスト58cm、ヒップ86cmのメリハリボディを披露。何となく着せてみた猫耳+黒ビキニ+ガーターストッキング+チョーカーが似合い過ぎな愛夏ちゃんに見つめられ、思わず鼓動が早くなる。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
サムの笑顔に心が温かくなる。努力と信じる力の大切さを教えてくれるフレンチアニメ 空を飛びたいネズミの奮闘を描いたアニメ。周囲の動物たちに白い目で見られながらも、純粋に夢を信じて前進する姿に共感。動物たちの表情も愛らしく、ほっこり癒やされる。 ある春の晴れた日、ツバメと共に大空を飛ぶという壮大にして突飛な夢を思いついた小さなネズミ・サム。彼は夢の実現に向けて、最大の壁となる重力の法則と森に暮らす動物たちの無理解に挑みながら、何とかして1年で夢を実現しようと奮闘する。
-
追加日:2020.1.20
社内にはびこるハラスメントに向きあい、解決していく痛快ドラマのスペシャル版 唐沢寿明と仲間由紀恵が共演。マルオースーパー、コンプライアンス室長・秋津はさらにパワーアップし、パワハラ騒動の裏に隠された真実に切り込んでいく。 老舗大手・マルオースーパーの本社乗っ取り事件の責任を取り、函館店の店長として働いていた秋津渉。だが別店舗で従業員の自殺未遂事件が起き、コンプライアンス室へ呼び戻される。また店の労働環境を調査すべく、過重労働撲滅特別対策班も動き出していた。
 Amazonプライムビデオで今すぐ観る
Amazonプライムビデオで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.20
核実験の中心地へ向かう調査団を通して放射能の恐ろしさを描いた短編ドラマ 原子力がもたらす恩恵を明るく語り、その当人たちが放射能の影響を受けて変わっていくさまが恐ろしい。ユーモラスなシーンと終盤との描写のギャップに胸が苦しくなる。 1961年のアルジェリアで、フランスによる4度目の核実験を行われた。放射性物質の採取と測定のため、7人の兵士による一団が派遣される。派遣団の一員である古参兵の大尉は、アルジェリアの地で、進化にとりつかれ変化していく世界の矛盾に直面する。
-
追加日:2020.1.20
身体から消えた縞柄を探す虎の子供の小さな冒険を描いたショートアニメ 水彩のような柔らかな絵柄で描かれる、小さな虎の子供の動きや身振りがとてもかわいらしい。個性に目覚め始めた子供の自覚や苦悩が、寓話的に優しく表現されている。 一面に広がる草原で走り回る小さな虎の子供たち。1匹の子供が、自分の身体にはほかの子供のような縞柄がないことに気づく。からかわれ、自信をなくした彼は、ふとしたことで川に流されてしまった。その先々で、虎の子供はさまざまなものを知っていく。
-
追加日:2020.1.20
現実と物語の世界の境界はどこに?観る者を翻弄するミステリアスな物語 車の運転中に起こした事故がきっかけで、不思議な世界に迷い込んだ男。どこからが現実で、どこからが架空の世界なのか、不思議とスリルに満ちたスリラー。 三面記者であるジョエルは、フランスの田舎で起こった事件の取材に出発する。その道中、犬を轢いてしまった彼が車を停めると、いつの間にか彼自身が普段したためている物語の中に迷い込んでしまう。彼は見知らぬ男たちに銃を向けられ、首輪を着けられて…。
-
追加日:2020.1.20
小さなネコの小さな世界は新しい旅を経てぐんぐん広がっていく ぬいぐるみのネコの奇想天外でユーモラスな旅の模様を描いたアニメ。独創性あふれるキャラクターたちの見た目と、予想できない旅の展開に思わずくぎづけになる。 ひょんなことから冒険の旅に出ることになった小さなネコ。気まぐれで周囲のペースに合わせることのできなかったネコが、不思議な出会いを通して少しずつ成長。相手の気持ちを思いやり、自分の感情をコントロールする方法を身につけていく。
-
追加日:2020.1.20
とある魚屋で繰り広げられる、魚たちによる壮大なオペラの夕べ 細やかなアニメーションで描かれる生々しい魚たちの表情、そして動きや表情からは想像できない美声と展開に胸をつかまれる。つい笑ってしまうラストの描写は必見。 舞台はとある魚屋。夜のとばりが下り、2匹の魚がソリストとなってヴェルディの「椿姫」を歌い上げる。臨場感たっぷりの指揮を執る魚の指揮者。美しく揃った声で盛りあげるさまざまな魚のコーラス隊。そして彼らの歌劇はついにクライマックスへ…。
-
追加日:2020.1.20
当初2020年に公開予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で1年延期となった、劇場版第24弾の映画『名探偵コナン 緋色の弾丸』。公開は2021年4月16日。今作では赤井秀一を筆頭に、メアリー、羽田秀吉、世良真純の「赤井ファミリー」が集結! 名古屋を舞台に、真空超電導リニアを絡めた大規模な事件が勃発する。また、今作のスペシャルゲストには映画『君の膵臓をたべたい』で、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した浜辺美波が抜擢されている。江戸川コナン(高山みなみ)たちは、鈴木園子(松井菜桜子)の招待で、4年に一度開催されるスポーツの祭典「WSG(ワールド・スポーツ・ゲームス)」に来ていた。鈴木財閥がスポンサーを務める日本WSG協会主催のパーティーでは、真空超電導リニアの開通発表も兼ねていた。そんな祝いの席で、突然の停電に乗じて園子の父・鈴木史郎(松岡文雄)が行方不明になってしまう。小嶋元太(高木渉)たち少年探偵団のおかげで無事、史郎は救出された。しかし史郎のゴルフ仲間である女性社長で、日本WSG協会のスポンサーが同様に拉致されていたことが判明。コナンは、15年前にアメリカで起きたWSGスポンサー拉致事件の模倣犯ではないかと疑いはじめる。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.21
キューブを獲得して、韓国合宿への切符を手に入れるのは誰だ?2PMやTWICEを輩出した韓国の大手事務所JYPと、ソニーミュージックによる共同プロジェクトが本格始動! 世界に通用するガールズグループを目指し、デビューをかけたオーディションを繰り広げていく。敏腕総合プロデューサーJ.Y.Park(パク・ジニョン)が日本8都市とハワイ、ロサンゼルスの全10ヶ所で地域予選をおこない、のべ1万人超えの参加者の中から選び抜いたメンバーが、韓国合宿に向けて火花を散らす。地域予選を突破した26名の参加者が、韓国行きの切符をかけて4泊5日の東京合宿に参加する。オーディション参加者には虹色のペンダントが渡され、ボーカル、ダンス、スター性、人柄のキューブを獲得してペンダントを完成させることが合格の肝となる。Part1では個人のダンス・ボーカルのレベルテストとスター性テスト、5つのグループに分かれて課題曲を披露するショーケースがおこなわれる。最終メンバーを目指し、実力をぶつけ合うガールズグループオーディションが今、幕を開ける!
 Huluで今すぐ観る
Huluで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.21
2PM、TWICE、Stray Kids等が所属する韓国大手事務所JYPとソニーミュージックによる共同GIRLS GROUP PROJECT「Nizi Project」始動。日本国内8都市、ハワイ、LAを含む全10箇所で開催したグローバル・オーディションの様子と、オーディションに参加した1万人超の応募者の中から総合プロデューサーJ.Y. Park (パク・ジニョン) 氏が直接選び抜いたメンバーによる東京合宿の模様をお届け! 最終メンバーまで残り、韓国JYPトレーニング合宿参加への切符を手にするのは果たして…?!
-
追加日:2020.1.21
3人の女たちの愛憎が引き起こした悲劇を描いたミステリー 片岡鶴太郎が主演を務め、執念の捜査で事件の奥底に潜む真相に迫る「終着駅」シリーズの第36弾。“雪螢”が導く殺人事件の切な過ぎる真相は、観る者の胸を打つ。 東京・新宿の空き地で、若い女性の遺体が見つかる。高級ブランド品を身に着けていたが、スマートフォンもバッグも見当たらず、身元は不明。臨場した新宿西署の牛尾正直刑事は、被害者のコートの襟に白い綿のような物が付着しているのに気づき…。
 Huluで今すぐ観る
Huluで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.21
2019年12月に導入されたパチンコ「AKB48」シリーズ最新台を最速実戦! 2人のAKB48ファンのライターが、“神スペ”と話題の新台の実戦に挑戦。その神スペと呼ばれるに相応しい出玉性能、卒業メンバーも続々登場する演出は見逃せない。 パチンコ攻略マガジンのライターであり、AKB48ファンでもあるシルヴィーと亜城木仁が、ファンの威信を懸けて「ぱちんこ AKB48 ワン・ツー・スリー!!」を最速実戦して連荘数で勝負。その神スペを体感すると共に、激アツ演出を一気に見せる。
-
追加日:2020.1.21
人気の「エヴァ」新作導入を記念したパチンコ実戦&バラエティ企画 2019年12月16日に導入された「〜シト新生〜」を最速実戦して、勝利を目指すファンのために解説。演出ドラフト会議はファンならば誰もが頷ける、エヴァ愛あふれる企画だ。 パチマガライターの優希、遊喜、眠井れむ、亜城木仁がパチンコ「新世紀エヴァンゲリオン〜シト、新生〜」の実戦と歴代「エヴァ」シリーズから演出を選抜するドラフト会議を実施。エヴァ愛に満ちた4人が最高のシーンを選び、「最強のエヴァ」を提案する。
-
追加日:2020.1.21
映画『フィードバック』は、謎の男たちがラジオ番組を占拠し、人気パーソナリティの真実の姿を暴いていくサスペンススリラー。深夜ラジオ番組「残酷な現実」でメインパーソナリティを務める主人公のジャービス役には、映画『おみおくりの作法』で知られるエディ・マーサンが抜擢された。監督はスペイン出身のペドロ・C・アロンソで、今作で長編映画デビューを果たした。また製作を務めたのは、『エスター』『フライト・ゲーム』『トレイン・ミッション』など、エンターテイメントとスリラーの融合に長けたジャウム・コレット=セラ。超高層ビルからお届けするラジオ「残酷な現実」。タイトル通り過激な放送をしていた、ラジオパーソナリティーを務めるジャービス(エディ・マーサン)はたびたび脅迫にあっていた。時代の流れから番組の打ち切りを局から打診されるも、耳を傾けないジャービス。いつも通りにスタジオに向かったジャービスは、ミュージシャンのアンドリュー(ポール・アンダーソン)とともに放送をおこなおうとした。しかし、突然謎のマスクを被った集団がスタジオを占拠。ジャービスたちは彼らの目的がわからないものの、指示に従っていく。そして彼らの目的が明らかになったとき、ジャービスの過去が明らかになる。彼が隠した残酷な真実とは?
 DMM TVで今すぐ観る
DMM TVで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.22
歴史に刻まれた数々の事件の真相を暴くドキュメンタリー 実際に事件に関係した人物のみが登場し、伝聞などではない証言者自身の体験を語っていく。脚色を排した証言の数々はリアリティにあふれ、より事件の大きさが伝わってくる。 史上最大の金融詐欺事件である「バーナード・マドフ事件」、コロンビア最悪の麻薬カルテルの壊滅、メキシコ湾原油流出事故の3つの大事件を取り上げる。関係者自らの証言でその事件が起きた経緯や裏側、犯行の手口など、真実を明らかにしていく。
-
追加日:2020.1.22
《土曜ワイド劇場》寝台特急カシオペア&スーパーひたち連続殺人追いつけない二つの列車の謎!美貌の女相続人の秘密朝9時25分、上野駅に到着した“寝台特急カシオペア”の車内で、アパレルメーカー社長・小野木由美(いしのようこ)の刺殺死体が見つかった。捜査を開始した警視庁捜査一課の十津川警部(高橋英樹)らが副社長の矢野豊(北山雅康)に聴取したところ、由美は仕事のかたわら、2週間前に行われた保険金殺人事件の裁判を傍聴するため札幌を訪れており、その日、帰京することになっていたという。その裁判とは、元クラブママの被告・福沢美登里(原田夏希)が山岳写真家の夫・明夫(池内万作)に1億円の生命保険金をかけて殺害した容疑に問われていたもので、明夫は由美の異母弟だったという。被告の美登里はマスコミから散々“悪女”と報じられていたが、起訴後に被告のアリバイを証言する目撃者が現われ、今回の一審で無罪を勝ち取っていた。由美はずっと美登里の無実を信じ続けており、無罪判決を喜んでいたらしい。(C)テレビ朝日・東映
-
追加日:2020.1.22
衝撃的な実際の事件をもとにした目を離せない物語が今シーズンも次々と展開する。題材として取り上げられる事件は、俳優ロバート・ブレイクの逮捕、ラッパー、ショーン・コムズの逮捕、議会研修生チャンドラ・レヴィ失踪事件、カリフォルニア州で実際に起きたピットブルによる襲撃事件など。さらに、9.11同時多発テロ事件の悲劇が影を落とす。エミー賞を受賞した人気ある顔ぶれに加えて、新たなレギュラー出演者も登場する。警察を率いるのは、レニー・ブリスコー刑事(ジェリー・オーバック)、エド・グリーン刑事(ジェシー・L・マーティン)、アニタ・ヴァン・ビューレン警部補(S・エパサ・マーカーソン)。検察チームには、ジャック・マッコイ検察官(サム・ウォーターストン)、ノラ・ルーウィン地方検事(ダイアン・ウィースト)に加えて、新たにセリーナ・サウザリン地方検事補(エリザベス・ローム)が参加。人質事件では全員が命をかけることになる。
 Amazonプライムビデオで今すぐ観る
Amazonプライムビデオで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.22
ワイルドリング、それは人でも獣でもない野生の血族。切なくも美しい青春ホラー! 『マイ・プレシャス・リスト』の若手演技派、ベル・パウリーがモンスターへ変貌していく少女を熱演。『アベンジャーズ』のVFXスタッフが手掛けた映像も必見だ。 森の一軒家で、「ダディ」という謎の男に監禁され、一歩も外に出ることなく育てられた少女・アナ。彼女が16歳の時ダディが自殺を図り、アナは女性保安官のエレンに保護される。だが、アナは「ワイルドリング」と呼ばれる呪われた血族の末裔だった。
 Amazonプライムビデオで今すぐ観る
Amazonプライムビデオで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.22
次女のパワーが覚醒!一家総出で悪を懲らしめるアメコミアクションの第2シーズン 父・ブラックライトニングを超えるパワーに目覚めた次女が大活躍。電気エネルギーを発する彼女が、電撃を自在に操る父、長女と共に、街にはびこる悪に立ち向かう。 家族と共にトビアスの攻撃を凌いだジェファーソン。だが、理事会は生徒の安全を考慮して学校を閉鎖しようとする。そんななか、次女・ジェニファーは自らの能力について悩み、長女・アニッサはフリーランドの人々に報いるための新たな方法を見つける。
 Amazonプライムビデオで今すぐ観る
Amazonプライムビデオで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.22
核開発、ミサイル実験の再開とますます先が読めない北朝鮮情勢。一方、国連による経済制裁が続いている北朝鮮国内では、スマホの普及、高級化粧品の販売など、一見活気に溢れているようにも見える。最近よく目にするのが「自力更生」というスローガンだ。意外なことに今、北朝鮮では競争原理や市場経済を取り入れた改革が導入されつつある。 識字率が高く地下資源も豊富で実は、経済的なポテンシャルは高いとの指摘もある北朝鮮。世界を振り回し続けるこの国は、いったいどこに向かおうとしているのか?さらに、60年前に「地上の楽園」と宣伝された帰国事業で、北朝鮮に渡った「日本人妻」たち。北朝鮮の地方都市で観た、驚きの生活とは?
-
追加日:2020.1.23
火曜サプライズは、旅とグルメで元気になる美味しい1時間! 日本各地の絶品グルメをはじめ、その街にまつわる楽しい情報をお届けします! スタッフによる事前交渉は全くなしの「アポなしグルメ旅」では、仕込みなしだからこそ起こる、予想外のハプニングや奇跡連発! ドキドキのアポなし交渉&台本なしの気さくなトークで、人気俳優&女優の皆さんの、他では見せない意外な素顔が見られます! さらに! 石原良純&長嶋一茂の暴走コンビとDAIGOが、ロケ時間60分で街の魅力を伝える「良純&一茂&DAIGOの60分一本勝負!」をはじめ、普通の旅番組とはひと味違った、楽しい企画が盛りだくさんです!
-
追加日:2020.1.23
執事との大切な毎日!新たな展開突入!新設定で恋も笑いもますますパワーアップ! 貧乏少年とお嬢様の執事ラブコメ第3期。原作者が原案を手がけたオリジナルストーリーを展開。前半のコミカル調から後半のシリアス調まで、新たな「ハヤテ」を楽しめる。 色々あった夏休みも終わり、いつもと同じ日常を送っていた三千院家。そこにネバダ州警察から「ナギの父親の遺品が見つかった」との連絡が。そのことにあまり興味を示さないナギだったが、そんな彼女の前に見知らぬ少女が姿を現し、衝撃的な事実を告げる。
 DMM TVで今すぐ観る
DMM TVで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.23
原作はクドカン&安斎肇!おばあちゃんロボットと女の子の日常アニメ、第3弾 人気脚本家の宮藤官九郎が物語を、イラストレーター安斎肇が挿絵を手掛けた、「小学一年生」連載の絵本をアニメ化。祖母型ロボットと主人公ひよりちゃんのおかしな毎日。 たくさんの流れ星がみられる日。一度も流れ星を見たことのないひよちゃんは、家族みんなと見に行くことに…(「第1話」)。歯医者さんが苦手なひよちゃん。ずっと虫歯を我慢していたけれど、とうとうママに見つかって…(「第2話」)。
 dアニメストアで今すぐ観る
dアニメストアで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.23
しょこたん原案!中川家の人々と愛猫・マミタスたちのドタバタ&ハートフルアニメ 愛猫家として知られる「しょこたん」こと中川翔子が、「マミタス」など自身の飼い猫たちをキャラクター化。魔法の力で「みらくるキャット」になった猫たちが大活躍! 東京の下町・谷中野(やなかの)に住んでいるポコ美、通称ポコタンは、勉強も運動も苦手。そんな娘を心配した亡き父・夏彦は、ポコタンの飼い猫「マミタス」に魔法の猫じゃらしを託す。みらくるキャットになったマミタスとポコタンたちのドタバタストーリー。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.23
わしもが今回もいろんなことに挑戦?ヘンテコなロボットギャグアニメ第5期 名探偵や町内会長、トレジャーハンターなど、わしもがいろんな職業に挑戦するようすがおもしろい。44話ではちょっと泣けちゃうわしもとひよりちゃんのエピソードも! おばあちゃん型ロボット・WASIMO(わしも)とひよりちゃんの、ヘンテコだけど楽しい毎日。いろんなことに興味津々のわしもは、名探偵になったりトレジャーハンターになったりして大活躍!?でもある日、わしもはロボット研究所に目をつけられて…?
 dアニメストアで今すぐ観る
dアニメストアで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.23
セントラル・パークで銃乱射事件が発生し、ほとんど女性ばかり15人が死亡。犯人は女性に恨みを持つ男だ。ブリスコー刑事(ジェリー・オーバック)と新しい相棒のグリーン刑事(ジェシー・L・マーティン、今回からレギュラー出演)は違法な自動小銃の出所を追跡する。容疑者(ゲスト・スター、ニール・ハフ)に迫るにつれて、職務でも私生活でも強引なグリーンのやり方に、ブリスコーは疑問を抱く。検察では、マッコイ地方検事補(サム・ウォーターストン)が殺人犯だけでなく、半自動小銃を大量殺人用に改造できると承知の上で販売した銃製造業者も起訴しようと決意を固める。
 Amazonプライムビデオで今すぐ観る
Amazonプライムビデオで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.23
もしもこの人がいなくなってしまったら…。イヌは創造力と辛抱強さで未来に立ち向かう 不思議な羊飼いと1匹のイヌが紡ぎ出すイマジネーションあふれる物語。ハイクオリティなCG映像、そして表情豊かなキャラクターから伝わる強い想いが観る者の胸を熱くする。 牧草地で1匹のイヌが羊飼いと幸せに暮らしていた。この羊飼いは羊毛を雲に変えて雨を降らせ、命のサイクルを永続させていた。だが羊飼いが永遠に生き続けることがないとしたら、谷はどうなってしまうのか。最悪の事態を避けるため、イヌはある行動に出る。
-
追加日:2020.1.23
夜の世界の中心・ナイトリングのNo.1ホストクラブ「クラブ・テキサス」の代表となった安藤シンタロウ(白濱亜嵐)は、自らの名を「ドリー」と改め、“貴族”としてこの世に生きる弱者を守り、全ての人が笑って暮らせる高貴な世界を作ることを決意する。そんな彼は、あるきっかけで聖ブリリアント学園の存在を知ることとなる。今や伝説の王子の“聖地”として、聖ブリリアント学園には転入者が殺到、「三代目伝説の王子」となった朱雀奏(片寄涼太)は世界中を廻り、王子道を邁進していた。貴族と王子、果たしてどちらが正義なのか-。ともに頂点を極める両者が出会った時、戦いの幕はすでに切って落とされていた‥‥。今、美しく尊い男たちが“伝説”の座を巡り、史上空前のバトルを繰り広げる! ?2020「PRINCE OF LEGEND」製作委員会
 DMM TVで今すぐ観る
DMM TVで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.24
1996年、今では80代となったソディが彼の姉とその家族を訪ねるところから物語は始まる。第2次世界大戦から半世紀以上がたった今でも、当時の激しい戦闘とその後の苦難がソディをさいなんでいた。ソディ老人は若いアマールと心を通わせ、ミャンマー(旧ビルマ)へ行くアマールに同行することを決める。アマールは、自由と民主化を求めて闘うミャンマーの学生を写真に撮り、写真エッセー・コンテストに応募するつもりでいた。ミャンマーへ発つ前にシンガポールで、ソディ老人はいくつかの地を訪れて昔を思い出す。それは英領インド軍の中尉だった頃で、ソディはシンガポールで美しい写真家マヤと出会ったのだ。彼女はソディに大きな影響を与えた女性で、彼は恋に落ちた。そしてマヤは後にインド国民軍に入隊する。 アマールと共にミャンマーを訪れたソディ老人。その2人をラニという女性が出迎える。ソディ老人たちは学生デモに巻き込まれ、それを制圧しようとした政府軍から発砲される。政府軍の兵士からアマールとラニが暴力を受けそうになり、その瞬間ソディ老人は若き中尉ソディに戻る。そして兵士2名を殺してしまう。政府軍の兵士たちに追われ、列車に乗り込んだソディ老人たち。その姿は、大戦中のソディたちに重なる。大尉となっていたソディは、一隊を率いて列車に乗っていた。だが英国軍の空爆を受ける。1944年、インド国民軍は疲労、寒さ、発熱、病気などに耐えてインパールに到着。兵力的に極めて劣勢の状況で、敵と戦うこととなった。ラニのバアバが建てたという学校へ行ったソディ老人。彼はそこでマヤの写真を見つけ、彼女が既に亡くなっていることを知る。ソディ老人はついに自分を取り戻し、アマールたちを逃がす。そしてミャンマーからインドへと国境を越えるよう指示をした。兵士の手榴弾によってソディ老人の体は吹き飛ばされる。だがその時、彼はやっとマヤとの約束を果たした。その約束とは「いつか必ず君の元に戻り、ずっと一緒にいるよ」だった。
 Amazonプライムビデオで今すぐ観る
Amazonプライムビデオで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
あなたは本当の“美しさ”を目の当たりにする。2019年度、女たちの華麗なる戦い 見た目だけではない、トータルの美しさが求められるミス・ユニバース。各国の代表たちが魅せる多種多様なパフォーマンス、そして感動的な優勝の瞬間に胸が熱くなる。 2019年12月9日(日本時間)にアメリカ・アトランタで開催されたミス・ユニバース世界大会の模様を収録。日本代表の加茂あこをはじめ、世界90カ国以上から集まった精鋭たちが知性、感性、人間性、誠実さ、自信、そして美貌を懸けて競いあう。
-
追加日:2020.1.27
今度の舞台は西部劇!?紐育星組の単独「ショウ」が新風を呼びこむ! 前年度までの「ライブ」から「ショウ」に名を変え、歌も芝居もパワーアップ!さらにオペラ歌手・北原瑠美がゲストに参加し、これまでのライブにはない魅力を醸し出す。 2013年7月、日本青年館大ホールにて開催された、紐育星組の単独公演。ゲストにオペラ歌手を迎え、歌も芝居も新鮮かつパワーアップ!今度のショウは西部劇。しかしゲストのオペラ歌手とスターファイブは一触即発!?波乱の舞台が幕を開ける!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
巴里花組の固い友情が舞台を熱く盛り上げる。巴里花組の魅力が深まる単独ショウ 今回のストーリーの主軸を担い、いつになく様々な表情を見せてくれるロベリアから目が離せない。シゾー、フィルブラン、レーヌの怪人トリオの狂言回しっぷりも見事! 2014年2月、天王洲銀河劇場にて開催された、『サクラ大戦』巴里花組の単独公演。巴里・シャノワールでは、ロベリアがいつになく不穏な表情を見せていた。シゾーたち怪人トリオの前にはロベリアを探す奇妙な男が現れ…。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
海水を抜いて貴重な水中遺物が現れるさまを、最先端のCG技術で再現するシリーズ第2弾 ニューヨークの街に沈む沈没船や、第一次世界大戦で活躍したUボートなど、心くすぐる沈没品を紹介。その検証によって、歴史的に重要な出来事の真実が浮き彫りになる。 最先端のCG技術を駆使して、誰も見たことがない海底の姿を露わにしていく。ニューヨークの街の下や、ゴールドラッシュで湧いた北米の各地にある水源、かつて戦場となった大西洋など、さまざまな水源の水を抜き、そこから垣間見える知られざる物語を綴る。
-
追加日:2020.1.27
これぞ究極のセクシー!リングで観客をメロメロにするあべみほがカメラの前でも躍動! 新日本プロレスのディーバとして活躍するグラビアアイドル・あべみほのイメージ。スレンダーでスタイル抜群の彼女が魅せるフェロモン全開のセクシーショットは必見。 “エロスの権化”あべみほがとっておきの官能ショットであなたを悩殺。すらりと伸びた脚を大胆に開脚したり、泡まみれの肢体を艶めかしくくねらせてみたり。徹頭徹尾全力投球で観る者を誘惑するみほちゃんの、持って生まれた天性のエロさにどハマり必至。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
まだ幼さの残る清水富美加の愛らしい笑顔&ビキニショットが満載 清水富美加改め千眼美子の名で女優活動に力を入れる彼女の貴重なイメージ集。ほんわかとした癒やし系のスマイルと初々しい水着姿を心ゆくまで堪能できるファン必見作。 テレビやグラビアで一世を風靡した清水富美加が、肉感的な水着姿と愛嬌たっぷりの表情であなたを魅了。接写で捉えられる彼女の無邪気な笑顔と時折垣間見せる大人びた表情にドキッ。均整の取れた水着姿もキュートこの上なく、何度でも繰り返し観たくなる。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
帝国歌劇団メンバーが大集結の記念すべきファースト音楽ライブ! 97年に開催された「サクラ大戦歌謡ショウ」の第1回公演。歌唱パートあり、ダンスあり、声優たち熱演のショートドラマパートもありの盛りだくさんな構成に熱狂間違いなし! 1997年7月、東京厚生年金会館で開催された「サクラ大戦歌謡ショウ」の記念すべき第1回公演「愛ゆえに」。帝国歌劇団の声優陣が「激!帝国華撃団」や「花咲く乙女」などを始めとする名曲の数々を熱唱し、踊り、ショートドラマをも熱演するステージ。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
豪華声優陣が贈る「サクラ大戦歌謡ショウ」、スケールアップした第2回公演 帝国歌劇団・花組の8人がついに集結。豪華キャストが3時間にもおよぶロング公演に挑む、その熱量は圧倒的。第1回公演からスケールアップした演出や美術の数々にも注目。 1998年8月、東京厚生年金会館で開催された「サクラ大戦歌謡ショウ」の第2回公演の模様を完全収録。第2回公演にして初めて帝国歌劇団・花組の主要キャスト8名が集結し、歌唱パートも劇中劇パートも、そのすべてが初回公演よりはるかにスケールアップ!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
カンナとすみれの熱演が光る、「サクラ大戦歌謡ショウ」第3回公演 桐島カンナと神崎すみれの2人が主軸となる本公演では、2人にしては珍しくシリアスで感動的な悲恋の劇中劇が展開されるのが最大の見どころ。珍曲「紅トカゲの歌」も必聴。 1999年8月、東京厚生年金会館で開催された「サクラ大戦歌謡ショウ」第3回公演。劇中劇「紅蜥蜴」の公演に向けて活動する花組のメンバー。富沢美智恵演じる神崎すみれと、田中真弓演じる桐島カンナの2人がメインの、躍動感あふれるショウが幕を開ける。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
20世紀最後の日を花組と共に。最初で最後の新世紀カウントダウン・ライブ 20世紀末、一夜限りの大晦日に豪華キャスト陣が集結し、『サクラ大戦』シリーズの数々のヒット曲をたっぷり熱唱。合間に挟まるトークコーナーも面白い情報満載で楽しめる。 2000年12月31日、青山劇場で行われた新世紀カウントダウン・ライブ。100年に一度の記念すべき節目に、主要キャストから脇を固めるサブキャストまでが大集合。20世紀末を盛り上げた『サクラ大戦』シリーズの数々の名曲たちを、21世紀に向け熱く歌い上げる!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
「サクラ大戦歌謡ショウ」第4回公演は、名曲満載で送るアラビアン・ストーリー マリア、レニ、織姫の3人が主役となる劇中劇は、アラビアンテイストでこれまでにないメロディが妖艶な雰囲気。もはや恒例の「カンナの妄想」シリーズには今回も爆笑必至! 2000年7月に東京厚生年金会館にて開催された「サクラ大戦歌謡ショウ」の第4回公演。アラビアの国、すれ違う兄と弟をテーマとした劇中劇は感動すること間違いなし。アラビアンテイストの音楽とキャストの迫真の演技によって、極上のステージが紡がれる。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
初歌も初笑いもここにあり!新春恒例歌謡ショウの記念すべき第1回 新春らしい華やかな衣装に身を包んだ華やかなキャスト陣が美声を轟かせる姿は圧巻。観客と視聴者の初笑いを奪っていく、冒頭の口上と「少年レッド」の喜劇も見もの。 2001年1月、東京青山劇場にて開催された「サクラ大戦新春歌謡ショウ」の第1回公演。ヒット曲の歌唱パートはもちろん、新春らしい初笑いをもたらす喜劇や、花組キャスト陣による太鼓の演奏、そして持ち歌と衣装を交換する企画など、今までにない試みが満載。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
オールキャスト総結集で送る、「サクラ大戦歌謡ショウ」五周年記念の第5回公演 泉鏡花の戯曲『海神別荘』を原作に、広井王子が独自にアレンジを加えた劇中劇を展開。五周年ということで豪華オールキャストが登場する絢爛なステージから目が離せない! 2001年8月、東京厚生年金会館にて上演された「サクラ大戦歌謡ショウ」第5回にして、五周年記念公演。泉鏡花の『海神別荘』を原作とした、海がテーマの壮大なストーリーを描く劇中劇。そして海に関する楽曲を歌いあげるキャスト陣の姿を見届けよ。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
巴里花組のメンバーが勢ぞろい。奇跡のファースト・ミニライブの様子を完全収録 『サクラ大戦3』の主要キャストが集まる、豪華な初ミニライブ。観客も一体となって盛り上がる「御旗のもとに」歌唱パートが熱い!まさかの笑えるゲストの登場にも注目!? 2001年8月に東京厚生年金会館で開催された、「サクラ大戦歌謡ショウ」シリーズ初の巴里花組ライブ。スケジュールの確保が不可能と思われた豪華キャスト陣が奇跡的に集結することができた貴重な公演。巴里花組の絢爛なステージに見惚れない視聴者はいない!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
「サクラ大戦新春歌謡ショウ」第2回にして、神崎すみれの感動引退記念公演 本公演をもって帝国歌劇団・花組を盛り上げて来た神崎すみれが引退することに。すみれを中心とした楽曲や演出の数々が涙を誘う。舞台を湧かせる超豪華ゲストの登場も必見。 2002年1月、東京青山劇場にて上演された「サクラ大戦新春歌謡ショウ」第2回公演にして、花組キャスト・神崎すみれの引退記念公演でもある。神崎すみれ愛にあふれた演目や楽曲の数々と、彼女を送りだすための最後の挨拶まで、号泣必至の感動が待つ。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
7人になった花組が挑む「八犬伝」!?生まれ変わった歌謡ショウが幕を開ける! 新春歌謡ショウで神崎すみれが引退したことで本公演から7人となる花組。舞台も青山劇場に変更され、セットや演出も大きく変わった、まさに「スーパー」な歌謡ショウ! 2002年8月、青山劇場にて開催された「サクラ大戦 スーパー歌謡ショウ」の第1回公演。神崎すみれが引退して7人になった花組だが、今回の演目に選ばれたのはなんと「八犬伝」!?8剣士が必要となるこの演目で、7人の花組はどう挑むのか。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
笑って泣ける人情喜劇とヒットパレード満載で送る、新春歌謡ショウ第3弾 「初笑い七福神」という題目がメインの第1幕では七福神に扮した花組の7人と、ダンディ団との笑えるステージを楽しめる。親方&千葉助の漫才級フリートークも爆笑必至! 2003年1月、東京・青山劇場、大阪・ウェルシティ大阪厚生年金会館大ホールにて開催された「サクラ大戦 新春歌謡ショウ」の第3回公演。七福神に扮した花組とダンディ団が送る、笑いあり、涙あり、踊りありの人情喜劇。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
大航海時代、夢とロマンを追う冒険をステージで再現!スーパー歌謡ショウの第2弾 世界中で愛される『宝島』を原作に、広井王子と『サクラ大戦』らしい味付けがされたステージは、テーマ性抜群。新曲もド派手な演出も満載で画面から目が離せなくなる! 2003年8月、東京厚生年金会館にて開催された、「サクラ大戦 スーパー歌謡ショウ」の第2回公演。世界中の子どもたちをときめかせる名作『宝島』を原作とした公演に挑む花組たち。子どもはいつ夢になるのか…深いテーマをはらんだ公演に感動不可避!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
サクラ大戦×新西遊記で贈るスーパー歌謡ショウの第3弾 演目が新西遊記ということもあって中国的な雰囲気を醸し出し、ロックな曲調の音楽も多めなのが歌謡ショウシリーズでも印象的。コメディとシリアスのバランスも絶妙! 2004年8月に東京厚生年金会館で開催された「サクラ大戦 スーパー歌謡ショウ」の第3回公演。花組オリジナル要素を取り入れた演目『新西遊記』と、それを作ろうとする中で巻き起こる事件を描くドラマが中心。ワクワクドキドキが止まらない舞台に大興奮!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
中嶋親方を巡るドタバタ人情喜劇を描く、新春歌謡ショウ第5弾 すごろくを使った新企画、芸の数々は爆笑不可避!スーパー歌謡ショウ「新西遊記」から繋がる舞台であり、伏線やリンクする部分が多々ある構成もおもしろい。 2005年1月に青山劇場にて開催された、「サクラ大戦 新春歌謡ショウ」の第5回公演。大帝国劇場の大道具係・中嶋親方が現職を辞めたがっている?それを思いとどまらせようと、花組たちは親方のもとを訪れて必死に説得を開始し…。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
新演出の導入、嬉しいゲストの出演など、見応え抜群のスーパー歌謡ショウ第4弾 2002年の新春歌謡ショウで引退をした神崎すみれが約3年ぶりに復活・ゲスト出演するのが最大の見どころ!また紅蘭が映像のみで出演するなどの新演出の試みにも注目。 2005年8月、東京厚生年金会館にて開催された「サクラ大戦 スーパー歌謡ショウ」の第4回公演。今回の演目は『青い鳥』が原作のアレンジストーリー。花組メンバーの舞台稽古中に起こる事件や、神崎すみれのゲスト出演が、ストーリーを大いに盛り上げる。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
根来幻夜斎の復活が花組を窮地に!?第6弾にして最後の新春歌謡ショウ! 2005年夏のスーパー歌謡ショウ「新・青い鳥」から物語が繋がるため、前公演を見るとより楽しめる。夏公演に引き続き、神崎すみれの出演、そして大喜利への初参加は見もの! 2006年1月、青山劇場で開催された「サクラ大戦 新春歌謡ショウ」の第6回にして最終公演。新年早々、死んだはずの根来幻夜斎が生きていたことが発覚。大神は幻夜斎との決着をつけるため行動する。シリアスなだけでなく、笑える大喜利も入った必見公演!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
初々しさも満点?な紐育歌劇団・星組初のレビュウショウ 紐育星組メンバー初のレビュウショウにもかかわらず、舞台上での息の合った芝居、歌とダンスを披露。そんな中で垣間見えるキャスト陣の初々しさもまた見どころ。 2006年3月、新宿文化センターにて開催された「紐育レビュウショウ」の初公演。紐育歌劇団・星組キャストにとっては初の大舞台。舞台上で魅せる歌もダンスも、そしてレビュウも、紐育の華やかな雰囲気に染め上げる。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
サクラ大戦歌謡ショウ10年の歴史に幕が下りる。感動のファイナル公演 ファイナル公演とうたうだけあり、これまで以上にシリアスな展開が盛り込まれ、ラストは涙なくして見られない。しかしコミカルな場面も多く、特にさくらのバニー姿は必見!? 2006年8月、青山劇場にて開催された「サクラ大戦歌謡ショウ」シリーズ感動のファイナル公演。華やかな幕開けを迎えるレビュウショウだが、1幕から帝国歌劇団・花組を巡る劇中劇が展開され、第2幕ではさくらに最大の危機が訪れる、10年の総決算!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
歌も踊りも芝居もパワーアップした、紐育星組のレビュウショウ第2回公演 帝都花組の歌謡ショウに比べ歌と踊りが多めのステージは、紐育星組らしい絢爛さ。星組単独ショウと武道館ライブの経験を経て進化した星組メンバーのパフォーマンスを見よ! 2007年7月、日本青年館大ホールにて開催された「紐育レビュウショウ」の第2回公演。紐育星組の単独公演としては2度目だが、3歌劇団が集結する武道館ライブを経たことでさらなる飛躍を遂げたメンバーたち。パワーアップした絢爛なステージで観客を魅了する!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
紐育星組3度目の公演にしてラストショウ 今回のレビュウショウのために書き下ろされたオリジナルソングも多数あり、ラスト公演に相応しいボリューム。過去の公演を超える最高のステージパフォーマンスに感涙必至! 2008年8月に銀河劇場で開催された、「紐育レビュウショウ」第3回にしてラスト公演。リトルリップ・シアターと紐育星組の絢爛なレビュウショウを見られるのもこれで最後…。スペシャルゲストも出演する最高のステージに、華やかなクライマックスが待つ。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
新曲もゲストも盛りだくさん!5年ぶりとなる巴里花組単独ライブ 巴里花組の単独ライブは5年ぶりだが、定番曲での盛り上がりやキャスト陣のコンビネーションは健在!新曲「巴里よ、目覚めよ」に始まり、主に2部では新曲を多数披露。 2009年12月、青山劇場にて開催された『サクラ大戦』巴里花組の単独ライブ公演。5年ぶりとなる巴里花組の単独イベントだが、新曲多数、サプライズ演出も満載の大ボリュームなステージ。それぞれの歌劇団からのゲスト出演もあり、巴里花組がより輝く!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
原点にして頂点の感動が再び。帝都花組、一夜限りの再集結ライブ 帝都花組に薔薇組、帝劇三人娘などおなじみのメンバーが大集合。さらにはゲストに巴里花組が登場しての、『激!帝〜最終章(フィナーレ)〜』大合唱は最大の見どころ! 2010年3月、東京厚生年金会館にて開催された『サクラ大戦』帝都花組による一夜限りの復活ライブ。2006年の歌謡ショウファイナル公演以来約4年ぶりとなる帝都花組単体公演。シリーズを支えた名曲に、歌謡ショウを思い出させる楽曲が心震わせる。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
巴里花組と紐育星組、2つの歌劇団が送る可憐で絢爛な豪華ライブ! 巴里花組と紐育星組の2歌劇団合同ライブは初となるが、その相性は抜群。それぞれが持つ華やかさと爛漫さを感じさせる曲の数々の調和、トークのキレのよさも素晴らしい。 2010年12月、青山劇場にて開催された『サクラ大戦』巴里花組と紐育星組、2歌劇団初の合同ライブ。歌劇団間での交流や賑やかなトークはもちろん、巴里花組の華やかな名曲と、紐育星組の絢爛なヒットソング満載で構成されるステージに熱く盛り上がる!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
歌も演劇もボリュームアップ。固い絆で結ばれた紐育星組の輝かしい舞台 今回のライブも新曲満載、さらには演劇パートのストーリー・ボリュームが大幅に強化され、これまで以上に作品の雰囲気が濃くなった。元欧州星組の集合も見もの! 2011年7月、日本青年館大ホールにて開催された『サクラ大戦』紐育星組の単独ライブ。3年ぶりとなる紐育星組の単独公演だが、元欧州星組の揃い踏み、多数の新曲披露など、圧倒的な見応えを誇る。スターファイブたちの「絆」の舞台、その輝きを見逃すな!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
初出演のキャストとともに作り上げる巴里花組単独ライブ フィルブラン役の高橋広樹、レーヌ役の野中藍がライブシリーズで初登場!これまで巴里花組のライブは歌唱パート多めだったが、ボリューム倍増の演劇パートが熱を高める。 2012年12月、青山劇場にて開催された巴里花組の単独ライブ。今回はおなじみの巴里花組メンバーやシゾーに加え、ライブシリーズ初出演のフィルブラン(高橋広樹)、レーヌ(野中藍)が登壇。華麗な歌とダンスも、波乱の演劇に花組が燃え上がる!
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
ある記憶を失った紐育星組の強い絆が試される。作品を深く掘り下げる注目の単独ライブ 大切な人の記憶を失った星組のメンバーたちが、その一大事を通じて気づく大事な想いの数々。「サクラ大戦」という作品そのものへの理解度も高めてくれる展開に感涙! 2012年8〜9月に日本青年館大ホールにて開催された、紐育星組の単独ライブ。謎の怪しげな人形によって「大切な人」に関する記憶を失った紐育星組の面々。果たして無事に記憶を取り戻せるのか。そして、大切なものを守ることができるのか…。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
新たなる敵は歴史上の有名悪党!人気アクションシリーズの第5シーズン 世界を救い、有名人となったレジェンドたちが究極の選択を迫られることに。第1話は巨大クロスオーバー『クライシス・オン・インフィニット・アース』のパート5。 レジェンドたちのドキュメンタリー制作が決まり、本来の任務から彼らの意識が離れていく。そんななか、地獄ではアストラ・ローグが歴史上最も有名な悪党たちを解放。レジェンドたちは、時間を混乱させる悪党たちを止めるべきか悩むが…。
 U-NEXTで今すぐ観る
U-NEXTで今すぐ観る
-
追加日:2020.1.27
受賞スピーチの中で見えてきたものは…。現実と非現実が入り混じるフレンチコメディ 監督は、短編映画を得意とするベンジャミン・クロッティ。独特の質感が印象的な映像とファンタジックなストーリーで、観る者を現実離れした世界へと誘う。 ナポレオン戦争を戦った農民兵士で、革命軍の退役軍人であるニコラ・ショヴァン。排外的な愛国主義を意味する言葉「ショービニズム」の生みの親でもある彼は、自身の功績を讃える賞を受賞するが、スピーチはいつしか身振りを交えた壮大な独白となっていく。





 動画を観るならDMM TV
動画を観るならDMM TV